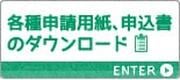日本の学校給食の歴史   | |
| 明治22年 (1889年) | 山形県鶴岡市の私立忠愛小学校で、仏教慈善団体が貧困児童に対する就学奨励のために実施したのが、我が国の学校給食の起源とされる。当時の給食は、おにぎり・焼き魚・漬け物だった。 |
| 昭和7年 (1932年) | 国庫補助による貧困児童救済のための学校給食が実施される。 |
| 昭和15年 (1940年) | 貧困児童だけでなく、栄養不良、身体虚弱児童も対象に含めた栄養的な学校給食が実施される。 |
| 昭和21年 (1946年) | 戦後、外国から送られてきた脱脂粉乳や缶詰を使用して、東京・神奈川・千葉の3都県で試験給食が開始される。 |
| 昭和22年 (1947年) | 全国の都市部の児童約300万人に対し、学校給食が開始される。 |
| 昭和25年 (1950年) | 8大都市の小学生を対象にアメリカ寄贈の小麦粉を使用したパンで完全給食が実施される。 |
| 昭和27年 (1952年) | 全国の小学校を対象に完全給食が実施される。 |
| 昭和29年 (1954年) | 「学校給食法」が制定される。 |
| 昭和39年 (1964年) | 学校給食に牛乳が供給されるようになる。 |
| 昭和51年 (1976年) | 学校給食に米飯が導入されるようになる。 |
| 平成元年 (1989年) | 学校給食100周年 |
| 平成9年 (1997年) | 「学校給食衛生管理の基準」が制定される。 |
| 平成17年 (2005年) | 「食育基本法」が制定される。 「栄養教諭制度」が実施される。 |
| 平成18年 (2006年) | 「食育推進基本計画」が策定される。 |
| 平成21年 (2009年) | 「学校給食法」が一部改正される。 学校給食120周年 |
| 平成22年 (2010年) | 文部科学省から「食に関する指導の手引き-第一次改訂版-」が刊行される。 |
| 平成23年 (2011年) | 「第2次食育推進基本計画」が策定される。 |
| 平成24年 (2012年) | 東日本大震災における原子力災害により、学校給食における放射性物質の有無や量を把握するため、「学校給食モニタリング事業」が実施される。 |
| 平成25年 (2013年) | 文部科学省から「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」の通知がされる。 |
| 写真提供 独立行政法人日本スポーツ振興センター | |
 明治22年 おにぎり、塩鮭、菜の漬物 |  昭和20年 ミルク(脱脂粉乳)、みそ汁 |
 昭和27年 コッペパン、ミルク(脱脂粉乳) 鯨肉の竜田揚げ、せんキャベツ ジャム |  昭和52年 カレーライス、牛乳、塩もみ くだもの(バナナ)、スープ |